Interview

起業家やアーティストのHUBとなり、世界と地域がフラットにつながっていくコミュニティをめざして
起業家に伴走するコミュニティビルダーが常駐するImpact HUB Tokyo。世界100以上の都市で展開されるコミュニティ「Impact HUB」の東京拠点として、また、地域にも開かれた形で、起業家やアーティストなどさまざまな人々が集い意見を交換し合う場として。今後の展望を代表の三塩氏が話します。
プロフィール
国際経営学の学士取得のためフィンランドに移住。パリやベルリンにも長期滞在し、ギャラリーや難民起業家支援団体での勤務を経験。株式会社Hub Tokyo入社後は、サステナビリティやサーキュラーエコノミー領域の起業家支援、新規事業の立ち上げ・戦略立案を推進。その後2024年夏より代表取締役に就任し、経営全般に携わる。
社会にインパクトをもたらす起業家やアーティストの集うHUBとして
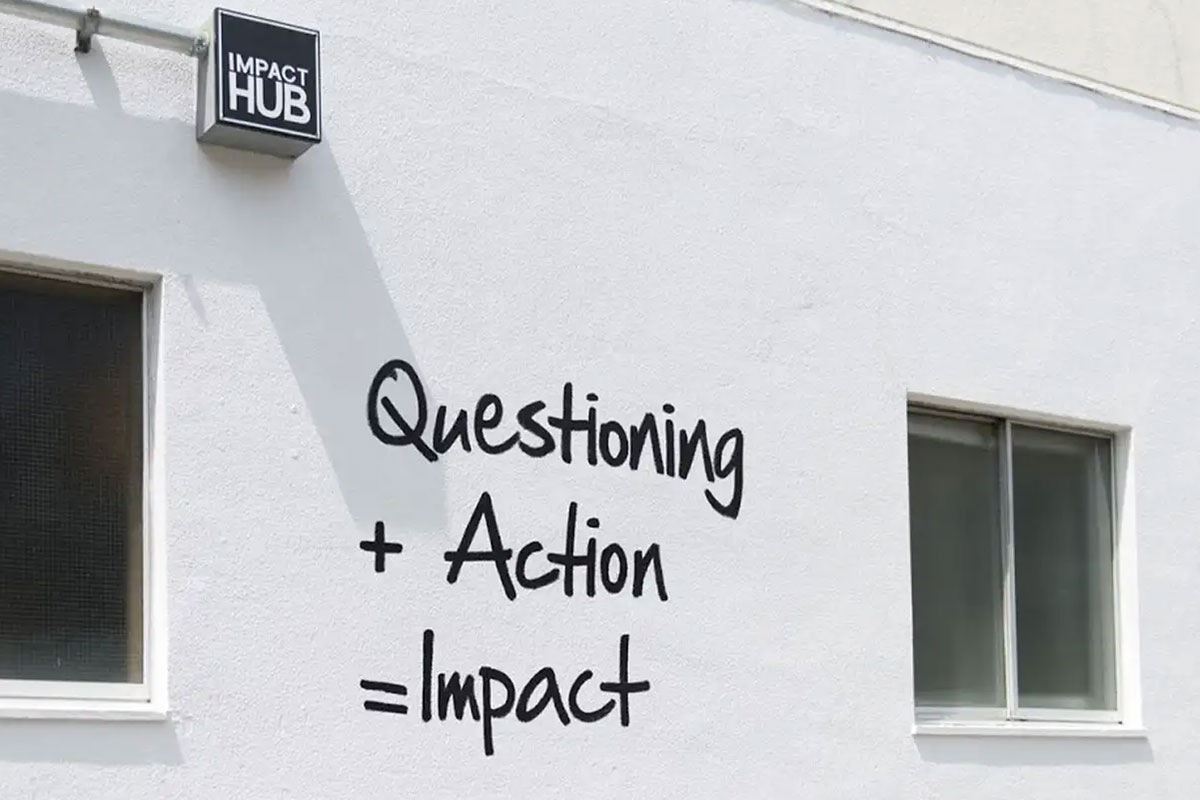
Impact HUB Tokyo はどのように運営され、どのように使われている場所なのか教えてください。
Impact HUB Tokyoは2013年頃に、起業家コミュニティとコワーキングスペースを提供する目的でオープンしました。単なる作業スペースではなく、起業家同士が悩みを相談・共有し合い、課題解決のための意見交換ができるコミュニティ文化を大切にしています。
建物は昔の印刷工場をリノベーションしており、古い家具を活用し、状況に応じてレイアウトを変更できる流動性なども重視しています。コロナ禍以前は「Team360」という起業家向けアクセラレーションプログラムなども実施していましたが、現在は場所とコミュニティの提供が中心となっています。コミュニティビルダーが常駐し、メンバー同士の紹介や毎月のランチイベントなど、起業家同士の出会いを創出する取り組みを行っています。
制度としては、月額のメンバーシップ制度(サブスクリプション)があり、複数のメンバーシップタイプを用意しています。会員になると、コワーキングスペースの利用、メンバー向けイベントへの参加、起業家向けプログラムへの応募なども可能になります。主にアーリーフェーズの起業家の方々が利用されています。
Impact HUB の成り立ちについて教えてください。
Impact HUBはロンドンで2005年頃に始まったグローバルネットワークです。もともとは起業家や投資家たちがパブで意見・情報交換をする中からそういった場所の必要性が認識され、コワーキングスペースの機能を持つコミュニティスペースとして発展しました。
現在では世界中に展開しており、グローバルなネットワークを活かして、海外からの利用者も多く集まっています。たとえば、ドイツのImpact HUBを利用していた方が、日本に移住した際に東京でのビジネス拠点として利用するなど国際的なコミュニティの接点にもなっています。
日本国内ですと、東京の他に京都にもImpact HUBがあり、それぞれが独立して運営されていますが、グローバルに連携し助け合いながらも各国の社会課題に取り組んでいます。世界中の拠点でも同様に、各地域の代表者やメンバーが独自の特色を持って運営していますね。
Impact HUB Tokyo の特徴はどういった点にあるでしょうか?
Impact HUB Tokyoの特徴的な点は、支援ではなく伴走という考え方とコミュニティビルダーという私たちの役割です。コミュニティビルダーは単なる受付や施設管理者ではなく、コミュニティの一員として非常にフラットな関係性を築いています。
また、入居企業は社会的ミッションが強い方が多く、クリエイティブな活動をする方も社会課題への意識が高いことが特徴かと思います。
会社としては名前にもある「インパクト」の本質を常に問い、安易に“社会的インパクト”という言葉を使わないよう心がけています。新しいコワーキングスペースが増える中、人間味のある泥臭い環境と、変化を恐れない組織文化が魅力です。
高校を卒業し、フィンランドの大学に進学。北欧・欧州で体得した“起業が当たり前”の社会へ

現在の運営チーム体制について教えてください。
2024年7月に代表交代があり、現在は私が代表取締役となりました。創業者2名も取締役として残っています。日々の運営は主に私とフランス国籍のレアさんの2名で、フルタイムで担当しています。
その他、創業期から関わっている業務委託のスタッフやカフェのパートタイムスタッフ、プロジェクトベースの業務委託などチーム全体では10名強で運営しています。以前はコミュニティビルダーが5、6人いた時期もありましたが、コロナの影響でオペレーションを変更し、現在はこのような体制となっています。
三塩さんのバックグラウンドについても教えていただけますか?
高校までは横浜の県立高校に通い、その後フィンランドの大学に進学しました。高校は英語教育に力を入れている学校だったこともあり、英語での論文執筆や第二外国語の学習など、国際的な教育を受けることができました。
私自身、両親がアーティストで自営業という背景もあり、早くから起業家支援、とくにアーティストや難民など社会的に立場が弱い人々の起業支援に興味を持っていました。
進学先にフィンランドを選んだ理由は、当時は外国人でも授業料が無料で英語での学士取得が可能という学費の面でもとても魅力的な条件があったこと。フィンランドではスタートアップ文化が発達していたこと。そして、ヨーロッパはもともと移民や難民が多く、そこから派生した社会課題や多文化共生に取り組む事業などさまざまな事例があったことなどが合致したためでした。
ヨーロッパでの経験についても是非、教えてください。
フィンランドで3年、フランスで1年、その後ドイツでワーキングホリデーを経験しました。フランスでは、難民の起業家と現地の起業家をマッチングして共同起業を支援する団体での活動がとくに印象的でした。ドイツのベルリンにいた時にImpact HUBと出会ったり、現地で多くのアーティストや起業家と交流したりする中でアーティストや起業家をバックアップしていく働きがしたいという想いが確信へと変わりました。
日本人としてのアイデンティティを大切にしつつ、大企業ではなく新しい形の仕事を探していた時に、Impact HUB Tokyoの存在を知ることができ、採用のタイミングも重なって入社に至りました。
起業家と対等に問いを立てて繋がる、コミュニティビルダーという役割と使命

コミュニティビルダーとしての役割や、起業家との関わり方について教えてください。
コミュニティビルダーは起業家と対等な立場でありながら、多くの場合若手として入社するため、起業家の皆さんのほうが人生経験も知識も豊富であるということはままあります。そのため、何かを教える立場というよりも、一緒に考え、事業の加速をサポートする役割を担っています。
具体的には、思考のきっかけを作ったり、事業が加速するための土台作りを一緒に行ったりします。コミュニティビルダーも時には自信を失うこともありますが、できることから取り組むというスタンスで支援を行っています。
コミュニケーションにおいては、どういったことを意識されていますか?
起業家との対話において、単に「YES」と言って受け入れるだけでなく、それが本当にその人にとって良いことなのか、「WHY?」を二度、三度と問い直しながら対応することを心がけています。オンラインで調べれば分かるような表面的な対話ではなく、きちんと問いを立てることが重要だと考えています。
Impact HUBのコミュニティビルダーとして、単に相手の言うことに同意するだけでは真の伴走にはならないという認識を持っています。
三塩さんご自身のこれまでの経験を通じ、日本とベルリン、フィンランド、パリなどでの環境にはどのような違いがあると感じていますか?
一つに、日本ではアーティストがまだまだ職業として認められにくいという特徴があります。
余程の有名アーティスト以外は生計を立てることが難しいという認識が強く、芸大進学も親に反対されるケースが多いです。
一方、とくにドイツなどヨーロッパでは、アーティストの職業が制度として確立されており、社会に認知されています。
起業家に関しては、日本でも近年はサポート体制が整いつつありますが、どちらかというとビジネスやサービス創造、社会課題解決に重点が置かれていますよね。
対してヨーロッパでは、起業すること自体は特別視されず、キャリアの選択肢の一つとして自然に受け入れられている印象があります。国によってはそもそも職が少なく、就職率が低いことが理由で起業に至るケースも多いので。大学でも起業関連の授業が普通に行われているなど、文化的な違いが顕著です。
つまり、アーティストが当然のように職業として成立する、そのために必要であれば起業する、という流れがよりノーマルに発生して社会にも存在するような環境を醸成して行きたいと、これまで私は考えてきました。
こういった意向から、アーティストのサポート体制は整えていきたく、かねてより私自身の目標でもあったアーティストインレジデンスのプログラムも、アーツカウンシル東京からの助成を受けて、作家の創作過程をサポートするという形で2023年に一期目のプログラムローンチに至ることができました。
アーティストと他の入居者との交流なども生まれているのでしょうか?
現在はまだアート展示など単発的な実施にとどまっていますが、展示期間中は入居者にとっても空間の変化が生まれ、良いリフレッシュとなっているというポジティブな意見をいただけました。
また、ここで制作をするアーティストにとっても、様々なタイプの方々からフィードバックを得られる機会となり、通常では出会えない異業種の方々との交流が生まれています。また、ビジネス的な観点からも有益な雑談ができるなど、双方にとって刺激的な機会になっているようです。
今後はこういった交流が展示期間のみならず、プログラムとしてより日常的に発生するような場づくりをめざしていきます。
施設の利用者層やこれまでに印象的な入居企業があれば教えてください。
現在、インバウンドで来日するビジネスパーソンやフリーランサーの方々の最初の接点となっており、海外からの利用者も増えていますね。
特徴的な入居企業として、「Le Wagon Tokyo」という英語でプログラミングを学ぶコーディングスクールがあります。当初は6~7人程度の小規模な生徒数でしたが、2017年から入居し、現在では30~40名規模のクラスを複数運営するまでに成長してきました。創業支援の一環として、初期段階では柔軟な賃貸料金体系を採用するなど、Impact HUB Tokyoとしてサポート体制を整えてきました。こうして、場をともにして風土を一緒に作ってこれた企業があることはとても貴重なことだと感じています。
アーティストや地域の人々とつながりながら、より開かれた形をめざす

今後の展開についてお聞かせください。
Impact HUB Tokyoは、施設としてはすでに10年以上の歴史があり、現在は新たなフェーズに入っています。
コロナ禍以降の大きな変化としては、まず、地域に開かれた形のカフェ「Deli at COMMUNITA」をオープンしました。これまでImpact HUB Tokyo自体はメンバーのみが利用できる閉じた空間でしたが、コロナ禍で心の距離が遠くなったことを踏まえ、より地域住民に開かれた場所をめざしました。
カフェではフリーWi-Fiを提供し、パソコン作業も可能(コンセント利用は不可)にすることで、一般の方々も気軽に利用できる空間となっています。カフェの常連のお客さまがスタッフと交流したり、公開イベントに参加したりするなど、新たなコミュニティの形成にもつながってきていますね。
また、代表交代に伴い、新しい世代で新しいことにチャレンジしていきたいという想いはありますので、今とこれからのチームの強みを活かしながら、新たな場所づくりをめざしていきます。
起業支援に関して、東京都などが提供するさまざまな情報やプログラムがオンラインなどでもアクセス可能になってきている中、私たちがこれまでに築いてきたカルチャーも補完的な役割を果たしていきたいと考えています。
とくに、アーティストとさまざまな業種の人々が交わり、お互いに刺激を与え合えるような場所づくりという意味で既存の起業支援制度も活用しながら、より創造的なコミュニティを形成していくことを計画しています。
Impact HUB Tokyoには、どのような方に利用してほしいとお考えですか?
ここは、グローバルにつながっているということが大きな強みの一つです。日本でビジネスを展開し、今後海外展開を考えているスタートアップチームには是非来ていただけると良いのではないかと思います。
また、気候変動やサステナビリティに取り組む企業の中でも、一時的なインパクトではなく持続的に取り組もうとしている方々や、本質を考えたいと思っている社会起業家の方々により多く来ていただきたいですね。
さらに、アーティストの方々も受け入れられるようなメンバーシップ制度の構築も検討しており、イベントやプログラム以外でもクリエイティブな方々が活用できる場所にしていきたいです。
INCU Tokyoというコミュニティに期待することや、今後どのような連携を希望されますか?
まず、私たちの施設がINCU Tokyoに登録されているということを内外問わず広く知ってもらい、さまざまな制度や情報を共有していきたいと考えています。
また、同様の施設が増えている中で、横のつながりを作りたいという想いでこのコミュニティに参加しました。単なる競争関係ではなく、お互いに協力できる関係性を築きたいと考えています。さらに、東京のスタートアップエコシステムについての理解を深め、その上でさまざまなコラボレーションの可能性を探っていきたいです。
とくに、場所を探している団体や予算が限られている団体、外国籍の方々による有志のグループなど、興味深いテーマを持つコミュニティとの交流をImpact HUB Tokyoは大切にしてきました。このような外部コミュニティとの交わりは、空間の活用という面でも重要で、新たな方々に施設を知っていただくきっかけにもなっています。
スモールビジネスや設立間もない団体の支援として、仮説検証の場として活用してもらえることをめざしているので、今後もイベントでのコラボレーションを積極的に進めていければ嬉しいです!
記載内容は2024年11月時点のものです。
