Interview
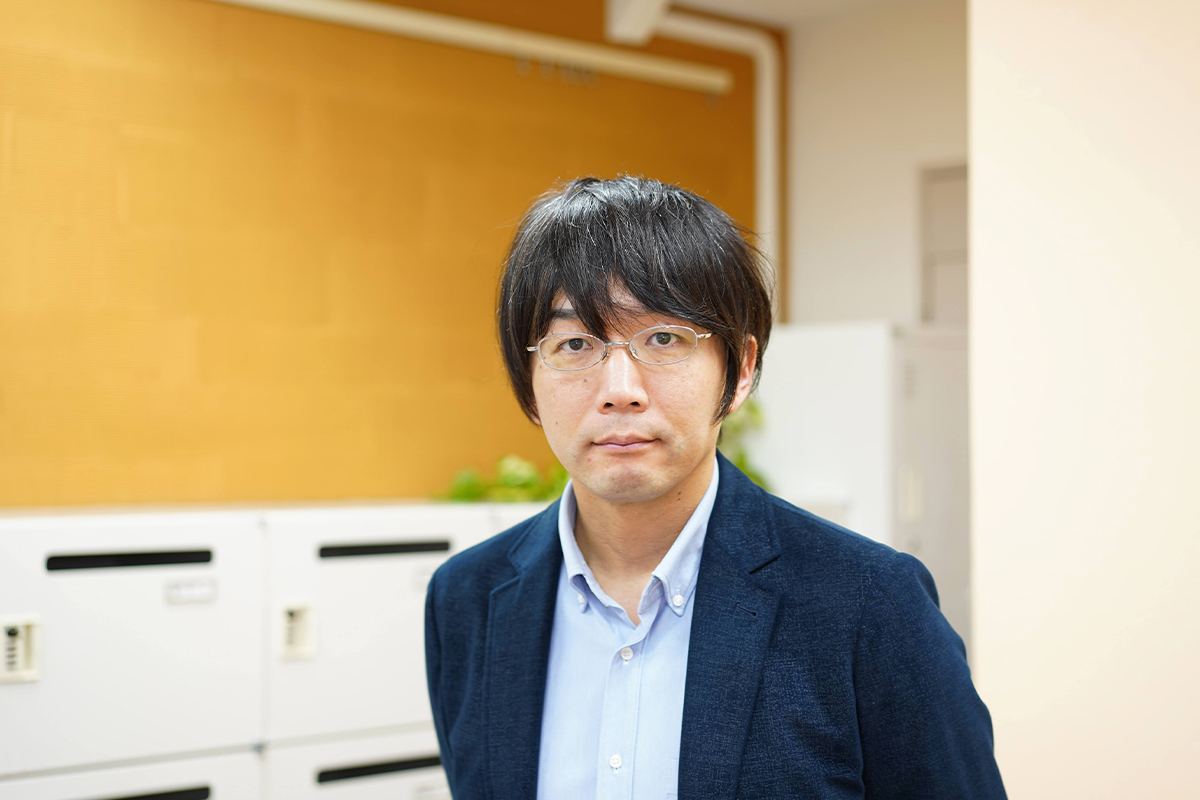
新宿で創業を支え13年。支援施設は「自分の知らない自分」を知り、世界を広げる場所
新宿区立高田馬場創業支援センターに2011年の立ち上げ時から13年以上に渡り携わっている田中 健一朗氏。中小企業診断士としての経験を活かしながら多くの創業者に対応してきました。「創業において最も重要なのは、誰がやるか」と話す田中氏が、支援の現場で見つけたやりがいとその魅力を語ります。
プロフィール
1980年生まれ、京都市出身。大学で人間工学を専攻。卒業後、美術大学で仕事をしながら中小企業診断士を取得。商店街イベントの立ち上げに従事した後、上京。中小企業診断士事務所で研修講師や調査業務を行いながら、たい焼き専門店の立ち上げに関わる。2011年から高田馬場創業支援センター所属、2015年より施設長。
実践的なセミナーと交流会で起業をサポート。高田馬場創業支援センターで広がるネットワーク

高田馬場創業支援センターの概要について教えてください。
2011年10月に新宿区役所が設置した創業支援施設で、新宿区内で創業をめざす方々をサポートする施設として日々運営しています。
高田馬場駅から徒歩約2分という好立地にあり、利用者の方々にとってとてもアクセスしやすい環境です。施設は、シェアデスクを中心としたフリーアドレスのシェアオフィスをメインとし、来客用の会議室や個室オフィスもあるなど利用者のニーズに応じた環境を提供しています。
民間のサービスと比較するとリーズナブルな価格設定となっており、登記や郵便物受取の代行、さらには個別に相談サービスも受けられるため創業初期のリスクを抑えながら挑戦できる環境を整えています。
そこでは、具体的にどんなサービスがあるのでしょうか?
センターのサービス内容は多岐にわたりますが、とくに力を入れているのは利用者一人ひとりの状況に応じたきめ細かな対応です。たとえば、会社設立や創業融資、補助金申請など創業時に必要な手続きのアドバイスだったり、専門的な知識が必要な場合は税理士や司法書士などの専門家に相談できる仕組みを設けたりしています。
さらに、月に1回の交流会を開催し、利用者同士のネットワークを促進しています。この交流会では、利用者や利用終了者が皆さんの事業について発表する機会を設けており、お互いの経験や知識を共有してもらえる場となっています。
また、一般向けのセミナーや国の産業競争力強化法に基づく区の特定創業支援等事業としての創業スクールを、4回に渡るシリーズで実施しています。創業経験者や実務経験豊富な方をゲストとして招き、よりリアルで実践的な内容を提供する取り組みを通じて、創業を選択肢の1つとして考えてもらえるような機会を提供しています。
縁を大切に、流れに乗って築いた創業支援のキャリア
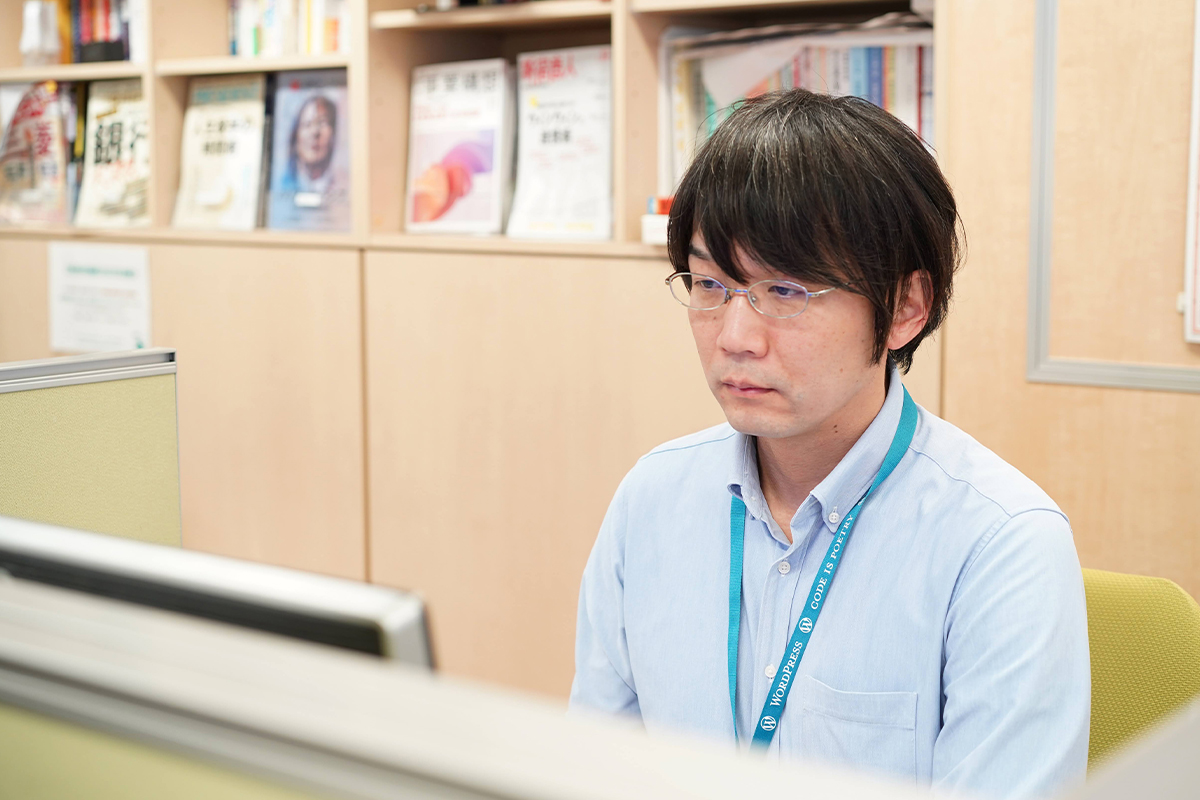
施設マネージャーに至るまでのキャリアや、始めた理由についてお聞かせください。
大学では将来性を感じロボット工学を専攻したものの、授業内容が難しくて卒業が危うくなりました。そこで単位互換制度を使い、経営学部で簿記を勉強することに。それがきっかけで公認会計士をめざして2年半ほど勉強しましたが、アルバイトと並行しながらやって受かるほど試験は甘くありませんでした。そこで、これまで勉強してきたことを生かせる資格は何かを模索し、中小企業診断士にたどり着きました。
資格取得をきっかけに、知人に中小企業診断士の方を紹介してもらいました。偶然、高校の先輩だったこともあって気にかけていただき、商店街活性化のためのイベント立ち上げに携わらせてもらったり、その方の事務所で研修講師や中小企業関係の調査の仕事などを経験させてもらったりしました。
その中で印象深いのは、たい焼き専門店の立ち上げに関わったことです。「なぜ、たいやき?」と思われる方も多いと思いますが、事務所の専門が商店街活性化だったことがきっかけでした。飲食未経験でしたが、商品開発や仕入れ先の開拓、内装工事、看板の取り付けなど一通り全部経験し、まさに「擬似創業体験」でした。短い期間でしたが、この経験が現在の仕事にも大いに活きています。
その後、高田馬場創業支援センターの立ち上げに声をかけてもらい、2011年のオープン時からスタッフとして関わることになりました。一度もちゃんとした就活をしたことがなく、流れに身を任せたようなキャリアですが、振り返ってみると自営業の家庭環境で育ったことも今の仕事に至った理由の一つなのかもしれません。
オープンから13年以上創業支援施設でキャリアを積まれてきた田中さんですが、仕事をする上で心がけていることはなんでしょうか?
日々の対応が積み重なることで、自分や社内に事例やノウハウが蓄積され、それが結果的に利用者や相談者の役に立てることにつながると思っています。そのため、コミュニケーションを大切にし、利用者と顔を合わせる機会をできるだけ増やすよう心がけています。
また、創業を言い換える言葉は、独立や開業、企業、スタートアップなど複数ありますが、スタイルが異なるのでしっかりと定義して対応するようにしています。たとえば「出資を受けた方が良いのか」という質問は、その方が将来めざす方向性によって答えが変わってきます。同じ相談でも「答えはひとつではない」ということに気をつけています。
コミュニケーションを取る中でお互いの認識をすり合わせることが、適切な対応ができるようになる一歩です。どのスタイルの創業がよいということはなく、その方に適したサービスを提供できることが重要だと考えています。そういう意味では、創業で大切なのは創業者自身が自分の現状を正確に把握し、相手に伝えられることかなと思います。
実体験が事業を動かす創業者の物語と、その成長を見守る喜び

仕事をしてきた中で印象に残っていることはありますか?
現場に長年携わってきた中で、どのような方が活躍したり、事業を継続したりしているのかということにふと気づくことがありました。それらの方の特徴として挙げられるのは、実体験に基づいた強い動機を持っている点です。
たとえば、ある方はご自身が障害者となり、訪問介護サービスに疑問を感じた経験から自ら訪問介護の会社を立ち上げました。また、引きこもりの経験がある方が不登校児童向けの学習支援塾を始めたり、特別支援学校で教員をしていた人が放課後デイサービスを立ち上げたりという例もあります。
彼らに共通しているのは、思いつきや儲けだけではなく、自身の経験や強い想いに基づいて事業を始めているということです。創業において最も重要なのは、「誰がやるか」という点です。ビジネスモデルやアイディアよりも、その事業を行う人物の経験や背景、動機が重要だと考えています。強い使命感や切実な想いを持っている人、または状況に迫られて事業を始めた人は継続する傾向があるということを確信しています。
そういう方々に関わる仕事のやりがいについて教えてください。
とくに、創業時に関わった事業者の成功や成長を目にすると嬉しく思います。具体的には、当センターを利用したことで事業がうまくいったと言ってもらったり、事業の近況報告を聞いたりする時です。また、利用終了後も困ったことがあれば相談にいらっしゃることもあり、そういった長期的な関係性も嬉しく感じます。利用者の事業が軌道に乗り、成長していく様子に触れられることがこの仕事をしていて喜びを感じる瞬間だと言えます。
INCU Tokyoとの連携でさらに広がる創業支援の未来

今後どのような方々に利用してほしいですか?
当センターでは「新宿で立ち上がる、走りだす、はばたく」をキャッチフレーズにしています。自身の経験や人脈、これまでの人生で培ってきたものを活かし、真剣に創業に取り組む方々のお役に立てるよう努めていきたいです。新宿で真剣に創業をお考えの方は、ぜひ気軽にお問い合わせいただければと思います。
個人的に私は「まずは人が自分にやらせたいことで創業するべきだ」と思っています。「自分がやりたいこと」がお金になるかわからない場合があるということと、自分がやりたいことは、自分が知っている範囲の中から選ぶことしかできないというのが理由です。
売上が立って事業を継続できれば、できることも多くなり、新しいことを知る機会も増え、やりたいことの幅も広がってくるはずです。やりたいことは変化するものです。今この瞬間の気持ちを優先しすぎるのではなく、10年後にやりたいと思ったことを、その時にできる強い自分をつくっていくことも大切かと思います。
人は案外自分のことをよく分かっていないものです。そのため、施設でスタッフや仲間から「自分の知らない自分」をフィードバックしてもらえる環境に身を置くことは、自分の世界を広げるために大変有効だと考えています。
最後に、「INCU Tokyo」に期待していることについて教えてください。
INCU Tokyoは、東京全体で創業する人を応援する姿勢を見える化している点で、とても素晴らしい取り組みだと考えています。
創業支援の方法は多様で、各施設のスタンスによって対応が異なります。たとえば、当施設では飲食店の創業支援も行っていますが、スタートアップ向けの相談施設ではそういった相談は想定されていないかもしれません。INCU Tokyo全体でさまざまな創業スタイルをサポートできる体制が整えば、より充実した支援が可能になると思います。創業者のニーズに合った適切な支援施設を案内できるようになり、東京全体の創業支援の質が向上することを期待しています。
記載内容は2024年10月時点のものです。
