Interview

異業種が出会い輝ける場所へ──クリエイティブを社会に広げるMaの挑戦
武蔵野美術大学の市ヶ谷キャンパス内にオープンした創業支援施設「Ma」。同大学の卒業生であり、この施設を支えるコミュニティマネージャーとして活躍する河野 奈保子氏が、入居者支援におけるやりがいやクリエイティブな視点で社会を広げる取り組みの意義について語ります。
プロフィール
武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科卒業。在学中に市民活動や生涯学習領域に関心を持ち、市民活動支援センター、NPO法人グリーンズなどで生涯学習講座の立ち上げ・運営を行う。現在はNPO法人soar事務局、武蔵野美術大学の非常勤講師としても活動しながら、コミュニケーションデザインを中心に日々学び中。
多様なキャリアを支援する、創造の交差点「Ma」

施設の概要や特徴について、教えてください。
私が勤務している「Musashino Art University Ichigaya Campus Co-Creation Space Ma(以下、Ma)」は、武蔵野美術大学の市ヶ谷キャンパス内にある創業支援施設です。2019年にオープンした8階建ての建物で、特徴的なのは施設全体で実現している多様な協働の形です。
この施設は、もともと六本木の東京ミッドタウンにあった「デザインラウンジ」の機能を引き継ぎ、教育や企業・地域との連携研究、そして働く人々のつながりの場として設立され、各フロアで企業や地域との連携を実現しています。
入居者の特徴や、サポートする上での独自性などはありますか?
Maが創業支援施設としてとくに注力しているのは、卒業したての独立するクリエイターのキャリアや創業支援です。じつは、武蔵野美術大学の卒業生の進路を見ると7~8割が就職を希望し、広告制作や新聞社のインハウスデザイナー、ゲームやサービスデザイン、プロダクトデザイン、カーデザイン、ファッションなど多岐にわたる分野で活躍しています。
一方で、約3割の「その他」に分類される卒業生の中には、在学中から外部との仕事を始め、卒業後も独自のプロジェクトを続けている方々がいます。アート系の学部であれば作家活動、デザイン系の学部であればデザインコンサルティングやクリエイティブ・ディレクター、デザイナーとしての活動を選択する卒業生も多く、従来の就職という形にとらわれない多様なキャリアが存在しているのですが、そういった方々への支援体制が十分とは言えない課題がありました。
そこでMaでは、クリエイティブに関わるさまざまな職種の方々が新しい協働の仕組みや仕事を生み出せる場をめざしています。現在、卒業生と外部からの約30人が入居しています。
毎月1回程度の交流会を開催し、普段顔を合わせる機会の少ない入居者同士が情報交換できる場を設けています。さらに、大学主催の勉強会やイベントを通じて、第一線で活躍するクリエイターとの出会いや、最新の大学の取り組みを知る機会も提供。比較的少人数の施設であるからこそ、相談や施設利用に関するリクエストにも柔軟に対応できる環境となっています。
学生時代のモヤモヤが原動力。制作から支援へと広がったキャリア
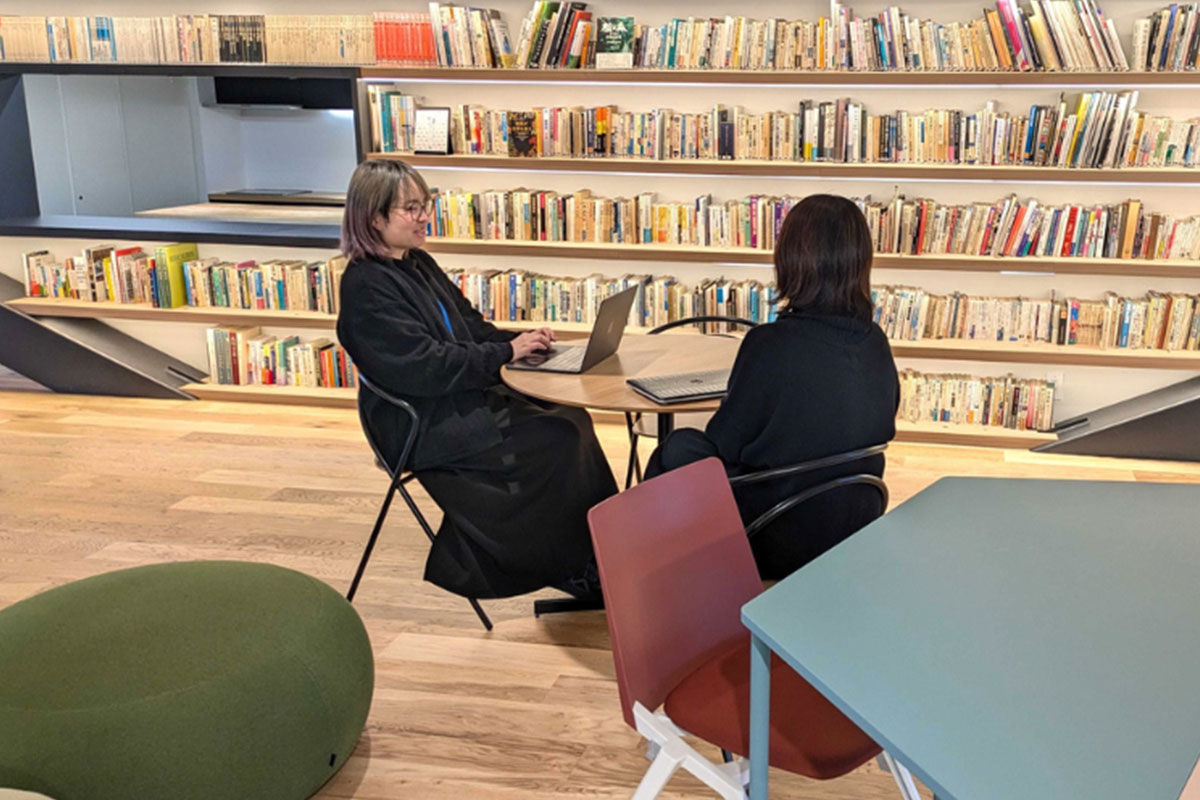
河野さんのこれまでのキャリアについて教えてください。
私は、武蔵野美術大学の視覚伝達デザイン学科を卒業しました。当初は広告制作をめざしていましたが、実際に手を動かして制作するよりも、制作する人たちと一緒に物事を作り上げていくプロセスに興味を持つようになったんです。しかし、当時はそういった職種の就職先が少なくキャリアの方向性に悩んでいました。
卒業後は母校の助手として、学生と教員をつなぐ役割を担当。その後、地域のボランティア活動支援の仕事に携わることになり、高齢者や障がいのある方、子どもたちとのワークショップを企画運営する機会を得ました。東日本大震災後は、都内の高齢者が多い地域で避難所運営のワークショップや、市民と行政の協働事業の相談窓口なども担当しました。
その経験を経て、ソーシャルデザインの非営利メディア「グリーンズ」で約4年間働きました。当時は地方創生ブームの真っ只中で、地域おこし協力隊や地域活性化に向けたさまざまな活動を始めている起業家の方々と、そういった活動に興味を持つ人たちをつなげる情報発信やイベントの企画、コミュニティづくりを担当していました。
この仕事を通じて、地域でビジネスを立ち上げる際には、デザインの力や物事を形にする能力が非常に重要だと実感しました。
実際に、建築やグラフィックデザインの分野で起業したり、社会課題解決型のビジネスを展開したりする武蔵野美術大学の卒業生たちとも多く出会いました。また、美大出身でない方々もクリエイティブの力を高く評価してくれており、そういった相互理解や信頼関係がおもしろいプロジェクトを生み出す原動力になっていると感じましたね。
そうした経験を通して、Maの仕事へと携わるようになったんですね。
そうなんです。約2年前、武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパスのコンセプトを考えていた職員の方々から声をかけていただき、現在の仕事に携わることになりました。私自身、学生時代に感じた「やりたいことはあるけれど、適切な場所が見つからない」というモヤモヤした気持ちを今でも覚えています。
だからこそ、新しい仕事やプロジェクトの形を提示していくことで、より多くの人が活躍できる場所を見つけられるようになればと考えています。
クリエイティビティを支える「種まき」に込めた想い

支援をする上で心がけていることは何ですか?
入居者の話に耳を傾けることです。入居者の方々は、それぞれに強い信念や意志を持っていますが、その想いは本人の中では整理されていても他者からは理解されづらいことも少なくありません。とくに、新しいプロジェクトの立ち上げや施設運営における課題が出てきた時には、相手が何に困っているのかをよく理解するよう心がけています。
日常的な仕事や生活の中では、自分のやりたいことを言語化する機会は少ないものです。そういった整理や棚卸しの場を提供し、アイデアを一緒に考えていく役割を果たせたらと考えています。
また、これまでの経験も活きています。たとえば、イベント企画やビジネスに関する相談を受けた際には、以前働いていたグリーンズでの経験や現在の仕事を通じて築いた人脈を活かし、さまざまな活動事例を紹介できます。とくに、クリエイティビティのある企業やコミュニティとのつながりを持っているため、相談内容に応じてサポートするようにしています。
メールで相談事をいただいたときなど、ついつい返信が長文になってしまうこともありますが(笑)、こうしたコミュニケーションの積み重ねが、物事の発展につながっていくと信じています。
創業支援に携わるやりがいについて教えてください。
さまざまな可能性の種があることを実感できることですね。種がいつ、どのようなタイミングで芽を出すのか、それにはどのようなサポートが必要なのか。これは私1人ではなく、施設に関わる多くの人々がそれぞれのタイミングでキャッチしながら支援を行っています。
試行錯誤を重ねる中で新しい何かが見えてくる過程にも、大きな魅力を感じています。私自身、絵を描くことが好きで人と競争するのは苦手でしたが、このリアルな場所が自分のキャンバスとなり、入居者の方々と一緒に未来を描いていけることに大きなやりがいを感じています。
異業種との協働が生む可能性──社会に開かれた創造のプラットフォームをめざして

今後、どんな起業家たちを支援し、何を実現したいですか?
武蔵野美術大学の卒業生はもちろん、さまざまな職種の方に入居していただきたいと考えています。デザインやアートの分野に限定せず、クリエイティブの可能性を感じてくださる方であればどなたでも歓迎しています。
現在の入居者からも「異業種の方が来てくれると嬉しい」という声をいただいており、多様な視点や専門性を持つ方々との協働に期待が高まっています。というのも、ビジネスや社会活動というのは、さまざまな役割を持つ人々の協力があってこそ成り立つものだからです。
美大という特色やクリエイティブな視点を大切にしながらも、それを閉じた環境にするのではなく、社会に開かれた創造的なプラットフォームとして発展させていきたいと考えています。
最後に、「INCU Tokyo」との連携への想いについてお聞かせください。
コミュニティマネージャーとして1年目の経験を活かしながら、さまざまな可能性を模索していきたいと考えています。とくに、クリエイティブ系に特化したイベントや勉強会の企画・運営には積極的に協力していきたいです。
新規創業者から長年の経験を持つ経営者まで、幅広い事例の共有や施設間の情報交換ができる場としてINCU Tokyoのネットワークを活用していければと思います。
施設同士の情報交換を活発にすることで、それぞれの特徴を活かしながら、より良い支援体制を築いていけたらいいですね。お互いに「どうしていますか」という素直な対話から始まる関係性を大切にしながら、インキュベーション施設としての成長をめざしていきたいです。
記載内容は2024年12月時点のものです。
